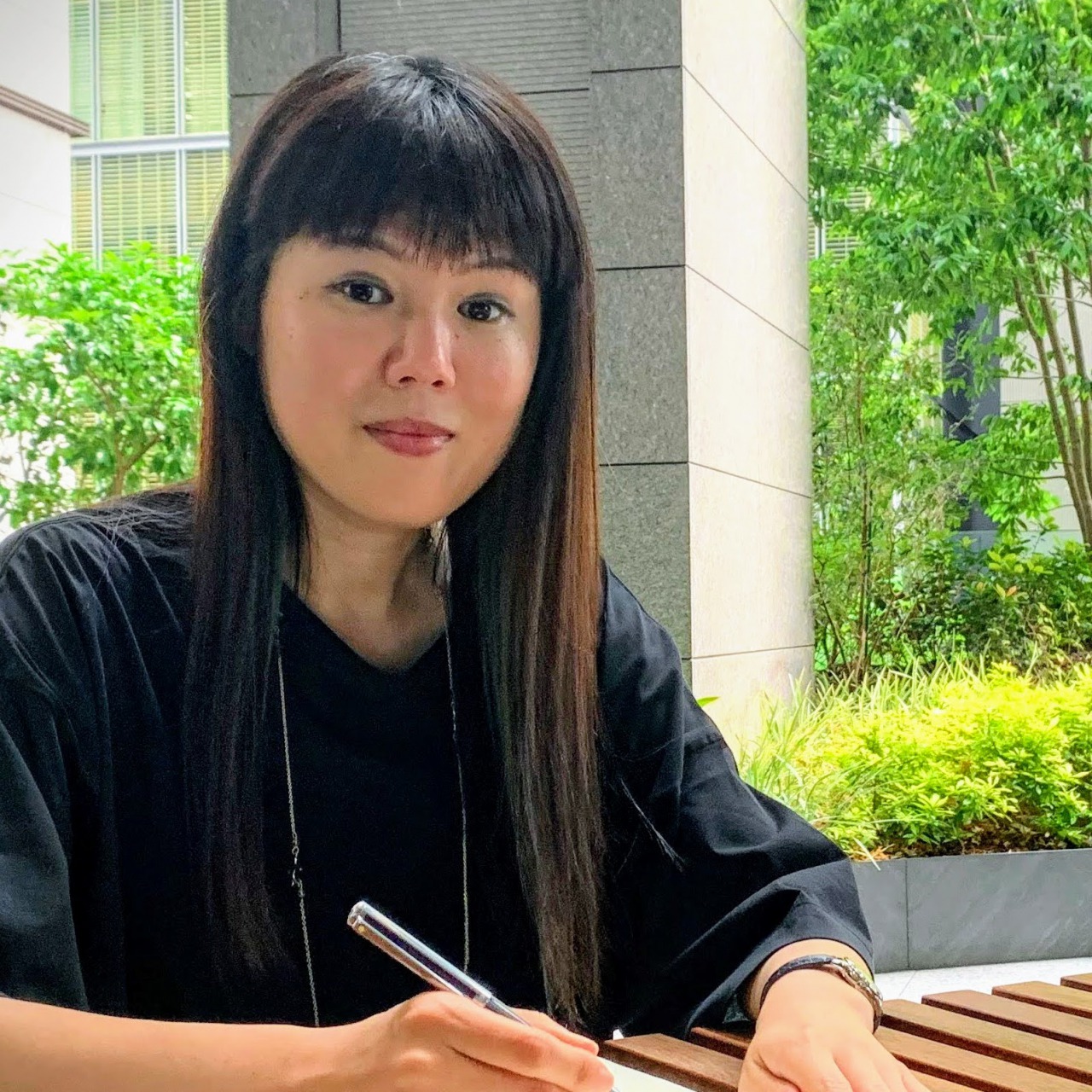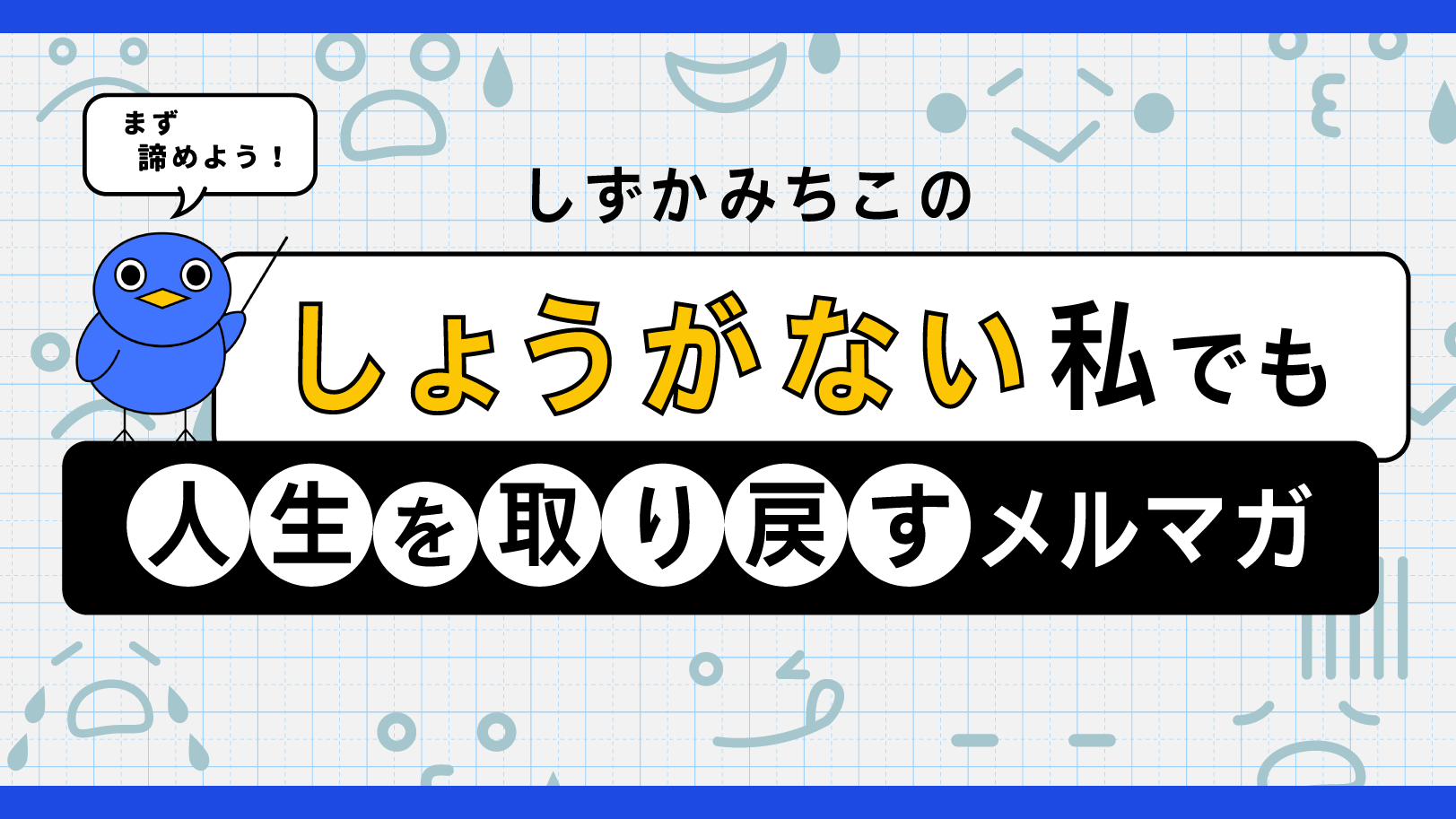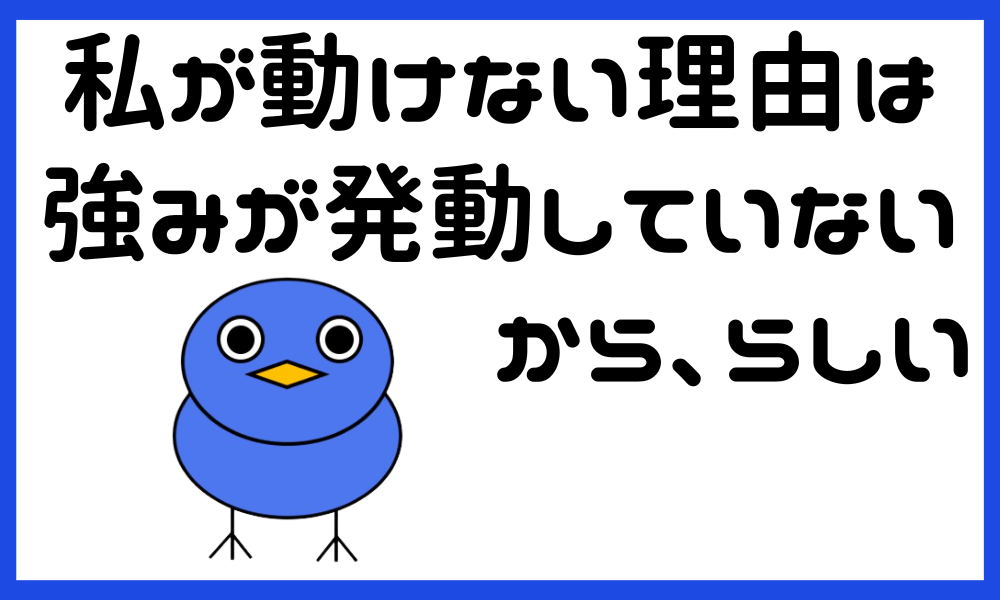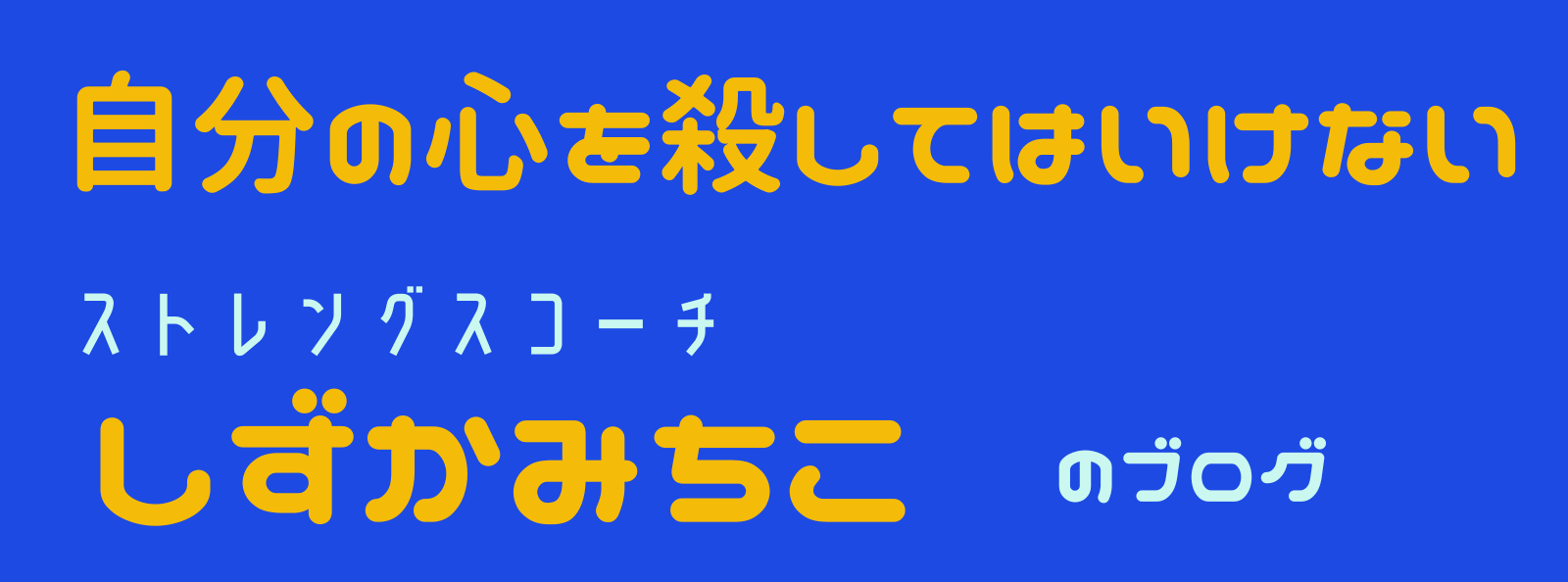『三島由紀夫vs東大全共闘』三島由紀夫が残した言霊を見た

私は、三島由紀夫が嫌いだ。
小説なのに文中に作者がしょっちゅう顔を出し、主人公たちのことを好き勝手に論ずる。
なんて出たがりの作家なのか。
『仮面の告白』は一回読んでお腹いっぱいになった。
読みやすい『金閣寺』や『潮騒』は繰り返し読んだ。
『豊饒の海』は途中で辟易して挫折したが、大人になっても何度も挑戦している。(まだ読みきれていない)
高校の資料室にあった新聞縮刷版で、三島が割腹自殺をしたときの記事を熟読していたあの頃から、嫌いなはずなのに気になってたまらない存在だった。
強烈な自己顕示欲と、それを紡ぐ美しい言葉。
磨き抜かれた肉体と、知的な光を湛えた鋭い眼差し。
三島由紀夫は、相反する魅力で私の心をがっしりと捉えているのだ。
『三島由紀夫vs東大全共闘』というタイトルの映画が上映されると知った瞬間にスケジュール帳を開き、最短の日程で予定を入れた。
初めて存在を知ってから30年以上経つのに、いまだに三島由紀夫の名を聞くと、私はじっとしていられない。
いったいどれだけ特別な存在なのだろう。
『三島由紀夫vs東大全共闘』
この映画は、1969年5月13日に行われた、三島由紀夫と東大全共闘の公開討論の記録映像だ。
当時の映像を中心に、ところどころ当時の関係者の解説が入る。
1969年の討論会は、今と雰囲気が全く違う。
例えば、全共闘で一番の論客と言われた芥正彦は生後半年前後と思われる娘を連れて来ている。
右手に火のついたショートピースを持ち、左手に娘を抱くその姿は、現在の常識では多くの批難が集まるだろう。
そういう側面も全て含んだあの時代の空気が、スクリーンに映し出された。
※ここから先はネタバレです。
50年前のドキュメンタリー映像に対してネタバレという表現が適切かはわかりませんが、映画の内容を踏まえて私が感じたことを書き綴ります。
駒場キャンパス
1000人以上の学生が待つ東大駒場キャンパス900番教室に、三島由紀夫は単身向かった。
三島を論破しやり込めて壇上で切腹させてやると学生が息巻いている討論会に一人で向かったのだ。
この討論会の4ヶ月前、全共闘は東大安田講堂事件と呼ばれる、投石や火炎瓶が多用され多数の警察官に怪我を負わせた事件を起こしている。
切腹させてやるという言葉も、あながち嘘には聞こえない。
その三島を心配し、三島由紀夫が率いる楯の会のメンバーがこっそり900番教室に紛れ込んでいたことは、私もどこかで読んで知っていた。
しかし、全共闘側も、三島を守るための護衛役を擁していたことは、この映画で初めて知った。
全共闘と対立する民青の乱入を警戒してのことだったらしい。
「言葉の有効性」
張り詰めた空気の中、まず最初に、三島がマイクを握った。
「言葉の有効性を確かめに来た」と三島は言った。
左翼の全共闘。
右翼の三島由紀夫。
立場の違う両者の間に言葉が通うのかを確かめに来たのだという。
そして、「言葉の有効性」は、確かに存在したのだ。
開始前は全面対決かと思われた討論会は、両者の間に通じ合うものさえ見出されたのである。
言葉が通じ合うとき
私がこの映画で驚いたのは、三島が終始余裕を持って、ユーモアを交えて話を進めること。
そして、学生側が聞くべきときは黙って三島の話を聞いていることだ。
お互い、感情的に言葉をかぶせて相手をやりこめようとするのではなく、相手を理解しようとする思いに満ちていた。
三島の自己顕示欲と、全共闘の激しさ。
私が持つ両者それぞれのイメージが覆された。
ではもともと学生側も穏やかに討論するつもりだったのだろうか。
それは違うと私は思う。
この討論会では、三島と壇上に上がった学生がお互いに敬意を持ち合っていることが感じられた。
この敬意は、三島が著名な文学者だから発生したものではない。
肩書きの有無で人を見る目を変えることを、全共闘の学生は嫌っている。
そこに敬意が生まれた理由は、2つあると思う。
自分の言葉
三島由紀夫は、冒頭から、自分をまっすぐにさらけ出していた。
学生からの挑発にも、正しいところは「それはそうだな」と応じ、豪快に笑って見せた。
自分の弱さ未熟さを、自分からさらけ出していた。
芥正彦は、そんな三島を挑発しつつ、真剣に話を聞き、議論を深めていった。
その芥が声を荒げるシーンがある。
議論を深める三島と芥に対し「三島を殴れるというから俺は来たんだ!」と観客の学生からヤジが飛んだときだ。
芥はその学生を壇上に呼んだ。
最初は話を聞いていたが、途中でその学生がどこかから借りて来た美しいだけの表面的な言葉を使って二人を揶揄したとき、芥は突然態度を変えた。
相手をあきらかに馬鹿にする態度を取り、もうこれ以上話を聞くつもりはないと打ち切ったのだ。
(なお、この間、三島は自分を殴ると息巻く学生に笑顔を見せている)
この件から、芥正彦は誰の話であっても大人しく聞くタイプではないことがよくわかる。
芥は、三島の言葉に三島そのものを感じ取り、そこに敬意を評して耳を傾けたのだろう。
知の裏付けある共通言語
この討論会の冒頭にこのようなシーンがある。
「他者とは何か」と問われた三島が「私の大嫌いなサルトルが、(中略)一番ワイセツなものは縛られた女の肉体だと言っているのです。」と回答し始めるのである。
「サルトル!?ワイセツ!?」と聞いている側は驚くのであるが、そこから暴力や闘争に繋ぎ、質問の回答に結びつく。
その後、芥正彦は、存在と観念についての議論に持っていく。
サルトルの実存主義が前提にある。
正直なことを言うと、このくだりの三島と芥のやり取りは私には難しすぎた。
この2人は、サルトルが書いた同じ本を読み、自分の言葉にできるまで深めているから、こういった議論ができるのだろう。
知性に裏打ちされた共通言語があるから、2人の話は深まっていく。
この知性にもお互いが敬意を評しあっている様子が伺える。
2020年のこの時代
2020年の今、三島の言う「言葉の有効性」は生き残っているのだろうか。
思想的にかけ離れたように思える人との対話は可能なのだろうか。
私は自分を振り返る。
私は、自分の言葉で語っているだろうか。
共通言語となりうる知性を持っているだろうか。
今の私に、死が毎日一歩ずつ近づいていることを教えてくれるのは、コルネイユではなく100日後に死ぬ一匹のワニだ。
でも1年後、私は、ワニのことを覚えているだろうか。
ワニが激しく炎上している最中も、コルネイユの作品は300年の時を超えて本屋の片隅でひっそりと悲劇を語る。
私は、時代を超える知識に裏付けされた自分の言葉を持っているのだろうか。
討論会の最後に三島が語った言葉を、ここに引用する。
「言葉は言葉を呼んで、翼をもってこの部屋の中を飛び回ったんです。」
「この言霊がどっかにどんな風に残るか知りませんが、その言葉を、言霊を、とにかくここに残して私は去っていきます。これは問題提起に過ぎない。」
時代は変わっても、私は「言葉の有効性」を信じたい。
三島の残した言霊を、私は確かに受け取った。