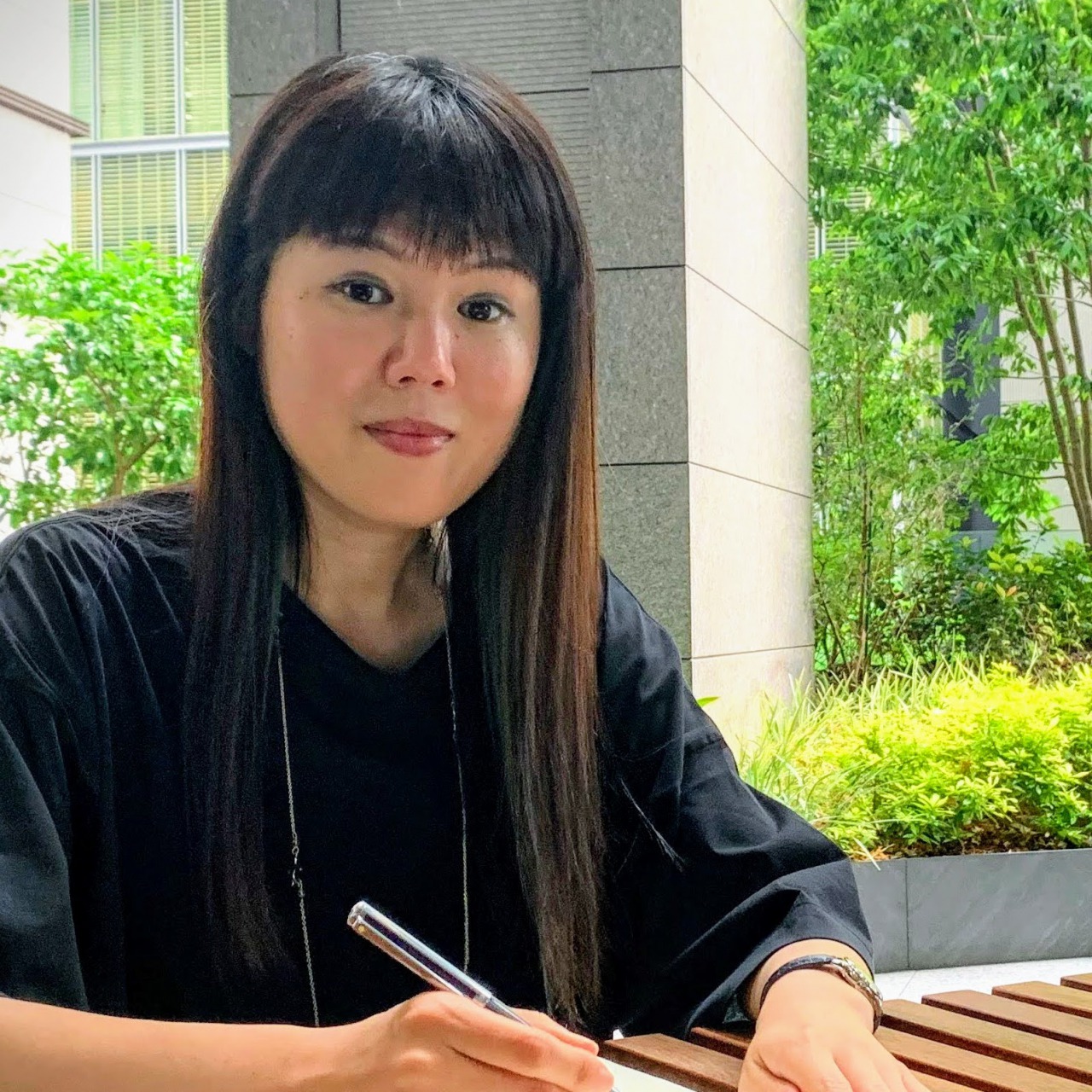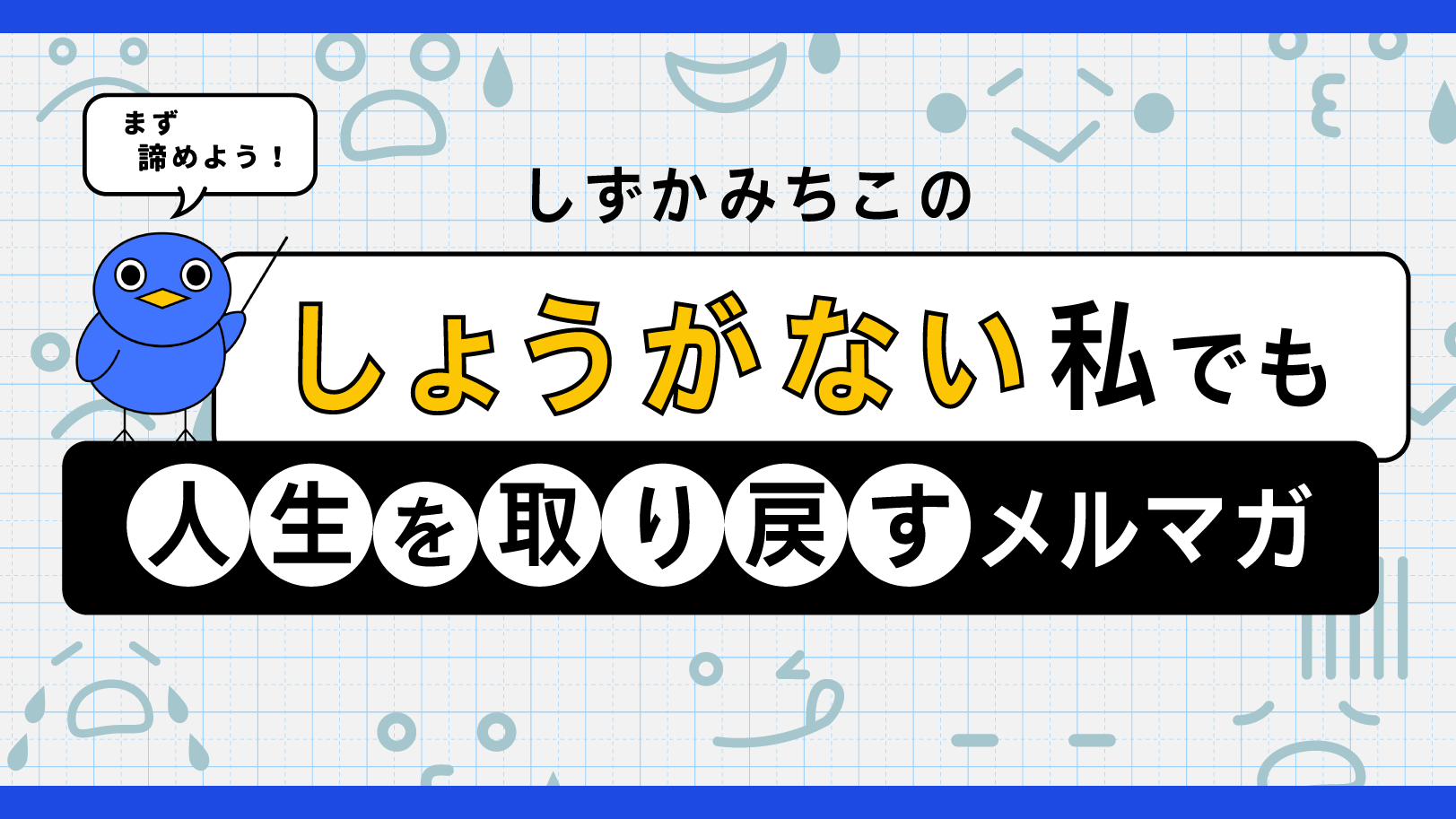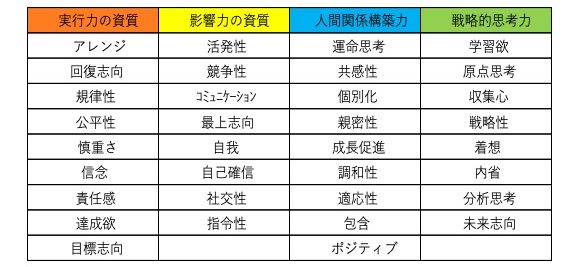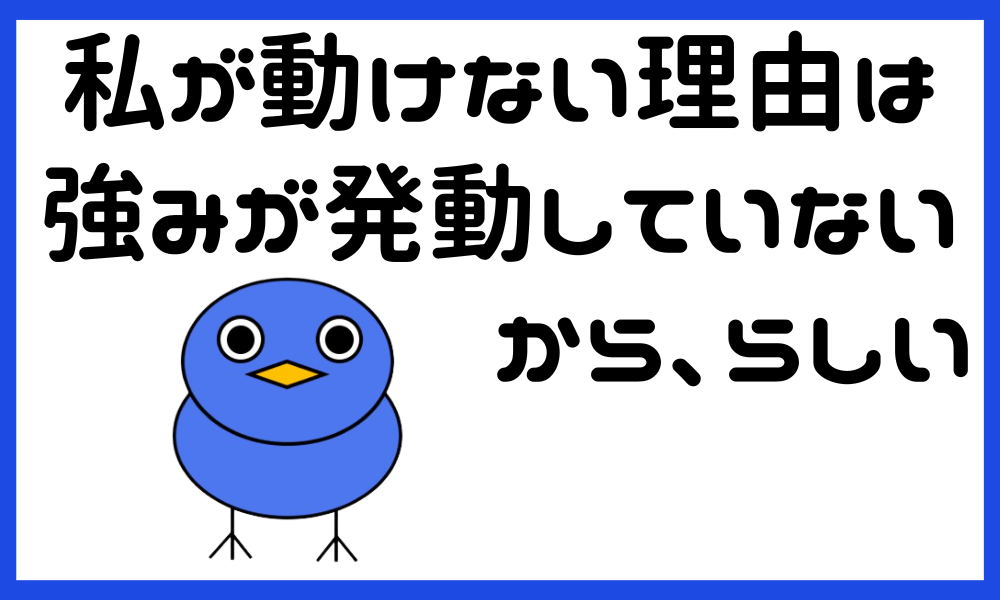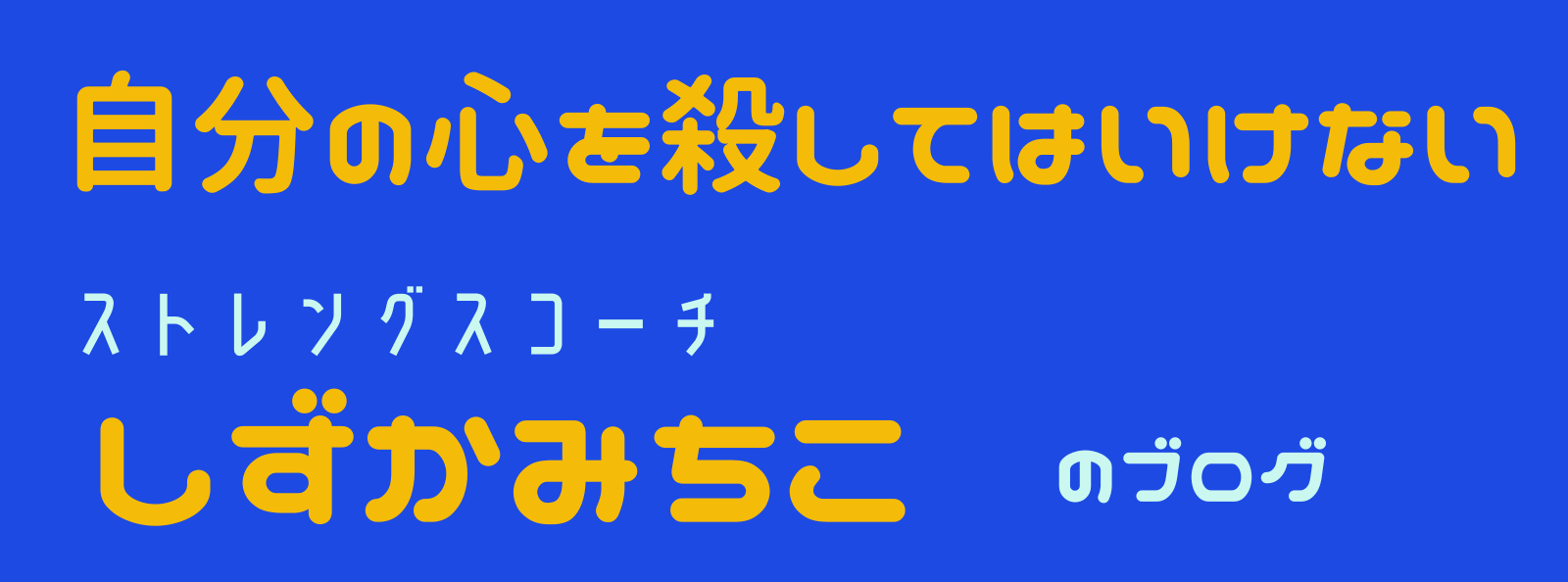芸術の力。いい絵や音楽や文章は、自分の心と化学反応を起こす

自分が空っぽだと絵も音楽も文章も役に立たない
いい絵、いい音楽、いい文章。
そう呼ばれるものが巷には溢れている。
でも他人がいくらいいと言ったって、それが自分に響くとは限らない。
いい絵や音楽や文章とは
絵や音楽や文章が自分の心を揺さぶるとき、人はそれを「いい」と判断する。
いい絵や音楽や文章は、自分の心にあるものと化学反応を起こす。
もしくは自分の心にあるものと化学反応を起こすものが、いい絵や音楽や文章となる。
どちらにしろ、自分の心の中が空っぽだと、化学反応が起きようがない。
いい絵や音楽や文章は、受け取り手の心があって、初めていい絵や音楽や文章となる。
いい絵や音楽や文章の中にあるもの
言い換えると、いい絵や音楽や文章と感じるものは、自分の心を投影しているものである。
その絵や音楽や文章の中に、自分の心と反応するものがあるから心惹かれるのだ。
絵や音楽や文章の中に散らばっている自分の心を探し出して、そっと集める。
絵や音楽や文章の力を借りて、自分の心を見つめなおすのだ。
人の器を大きくするもの
生きていると、いろいろなことを経験する。
その経験を通して感じたことが、自分の心の中に積み重なって、自分というものができていく。
その経験が増えていくと、心の器が広くなり、人間として大きくなっていく。
いい絵や音楽や文章の効果
絵や音楽や文章は、経験を補うものでもある。
自分の心の中のとある経験にそっと寄り添い、それを違う角度から見せてくれる。
「ああ、あれはこういうことだったのか」という気づきをもたらしてくれる。
いい絵や音楽や文章は、自分の心と化学反応を起こして、心を深く豊かにしてくれるのだ。
心を深く豊かにするもの
人間の器という言葉がある。
心が深く豊かで許容範囲が大きいと、器が大きいと呼ばれるようになる。
人間の器とは、これまでにどんな経験をしてきたかで育つのではないだろうか。
不可能と思ったことに挑戦して、乗り越えたとき。
不可能と思ったことに挑戦して、挫折したとき。
自分の限界を乗り越えた経験も、自分の限界を思い知った経験も、真剣に向き合った結果であれば、どちらも心に刻まれて心を深く豊かにしてくれる。
いい絵や音楽や文章の力
しかし、人間が生きていて経験できることには限りがある。
そこを補うのも、絵や音楽や文章だ。
一見では理解できないものに向き合う。
理解できそうにないものを咀嚼して受け入れる、もしくはどんなに咀嚼しても受け入れられないと断念する、もしくは咀嚼すらできないことを受け入れる。
自分が理解できないものに対して、真剣に向き合い、その結果を受け入れる。
この過程によって、自分の心にあるものとないものを知り、心が深く豊かになる。
これを繰り返し、人としての器が少しずつ大きくなる。