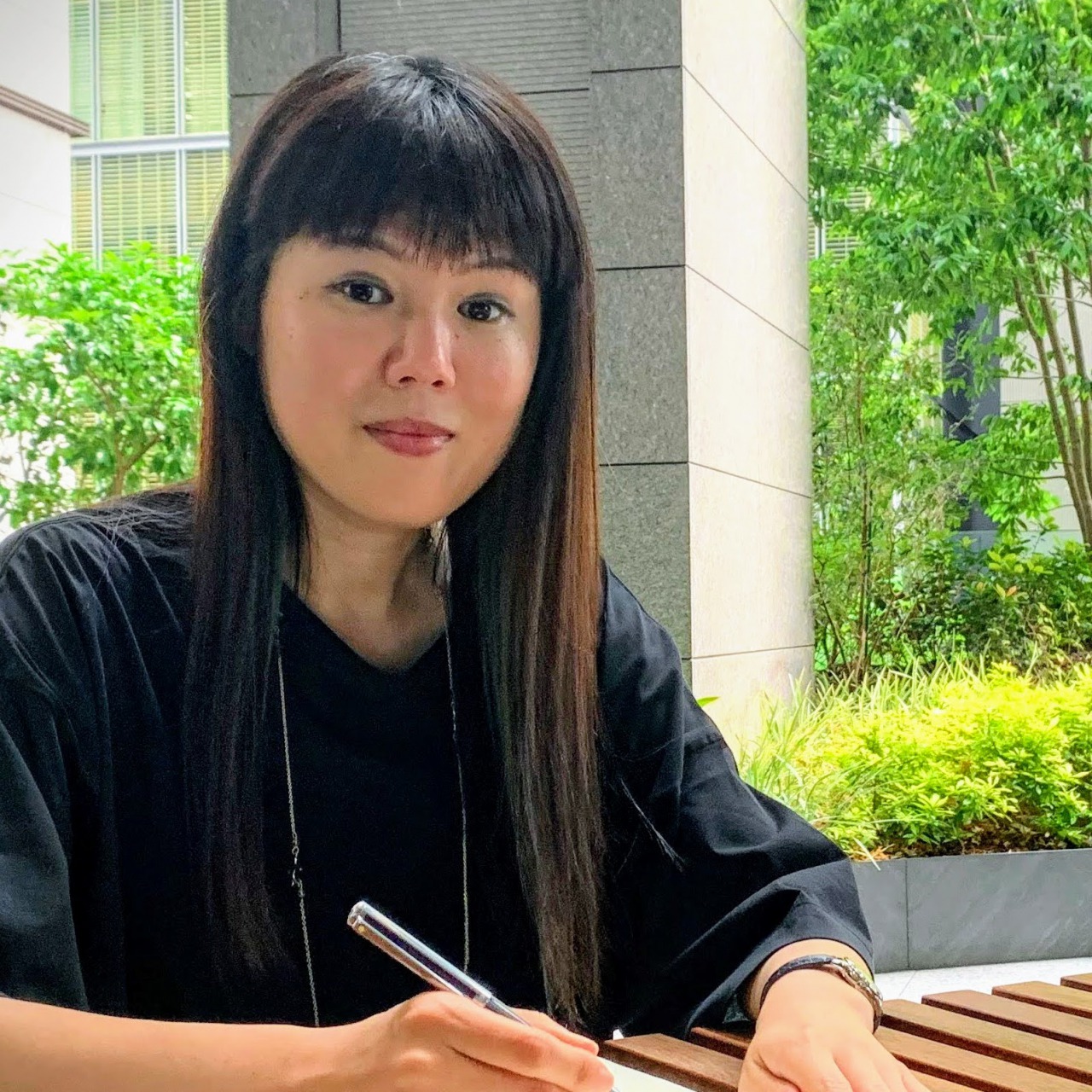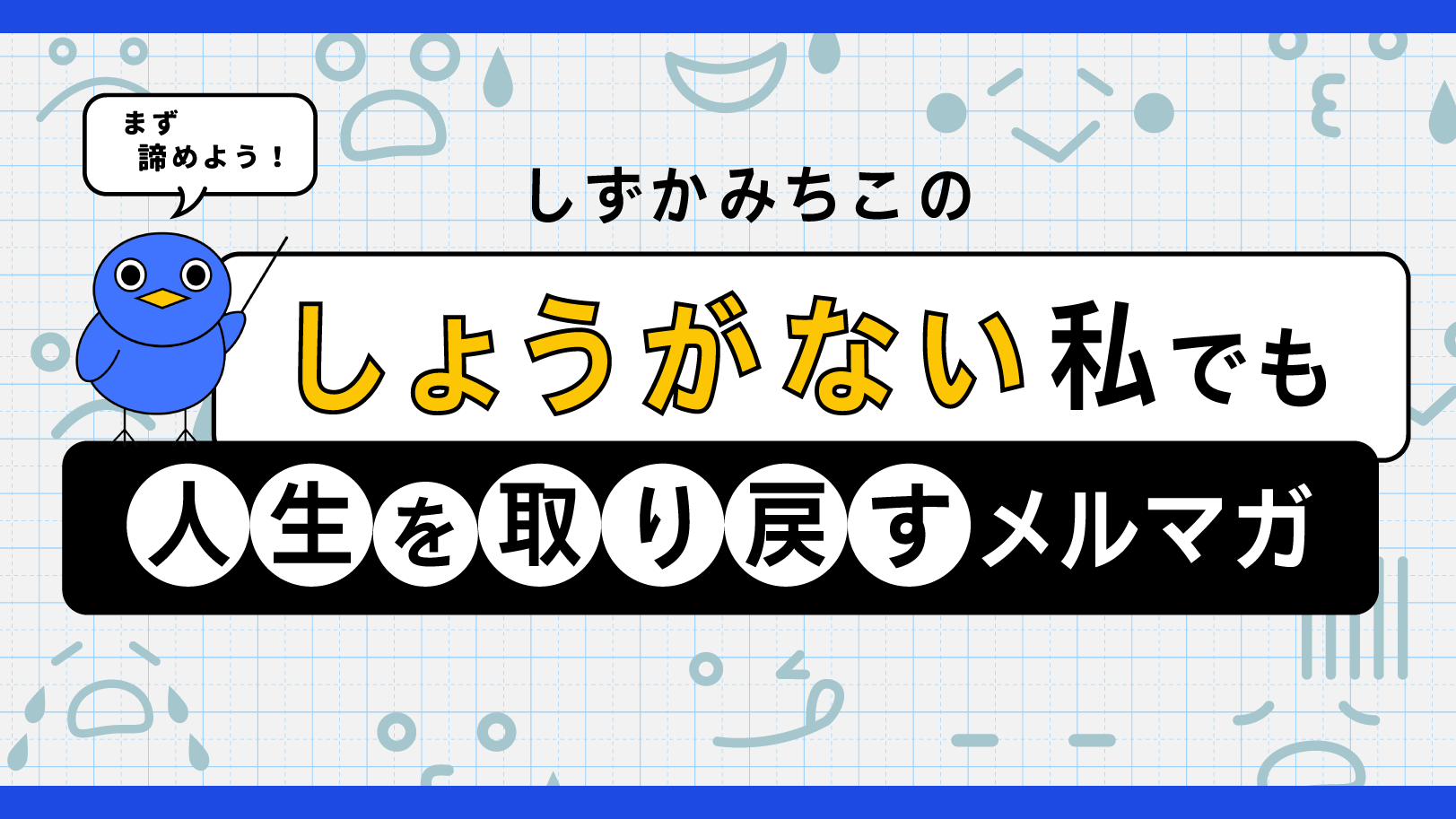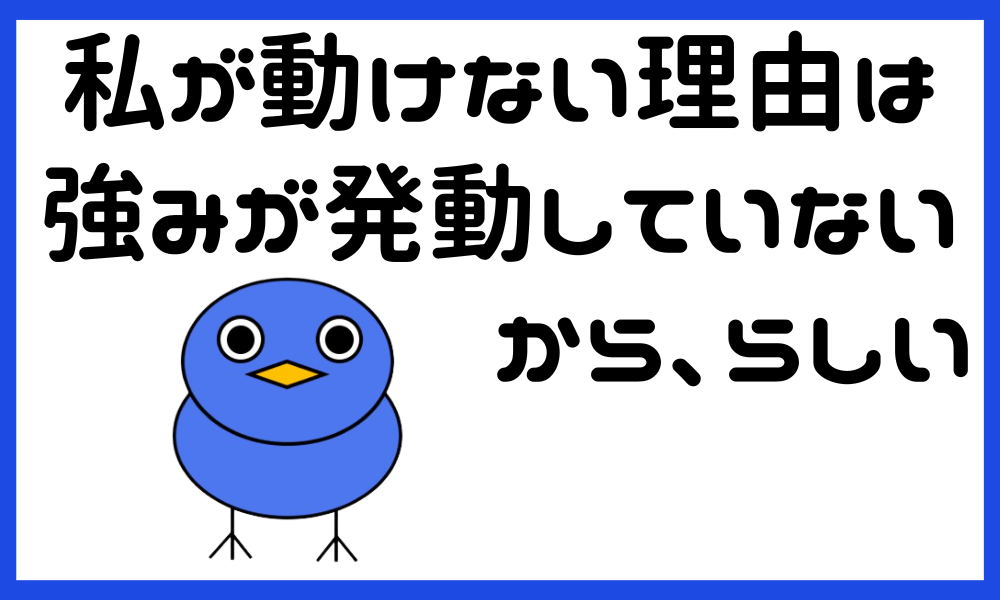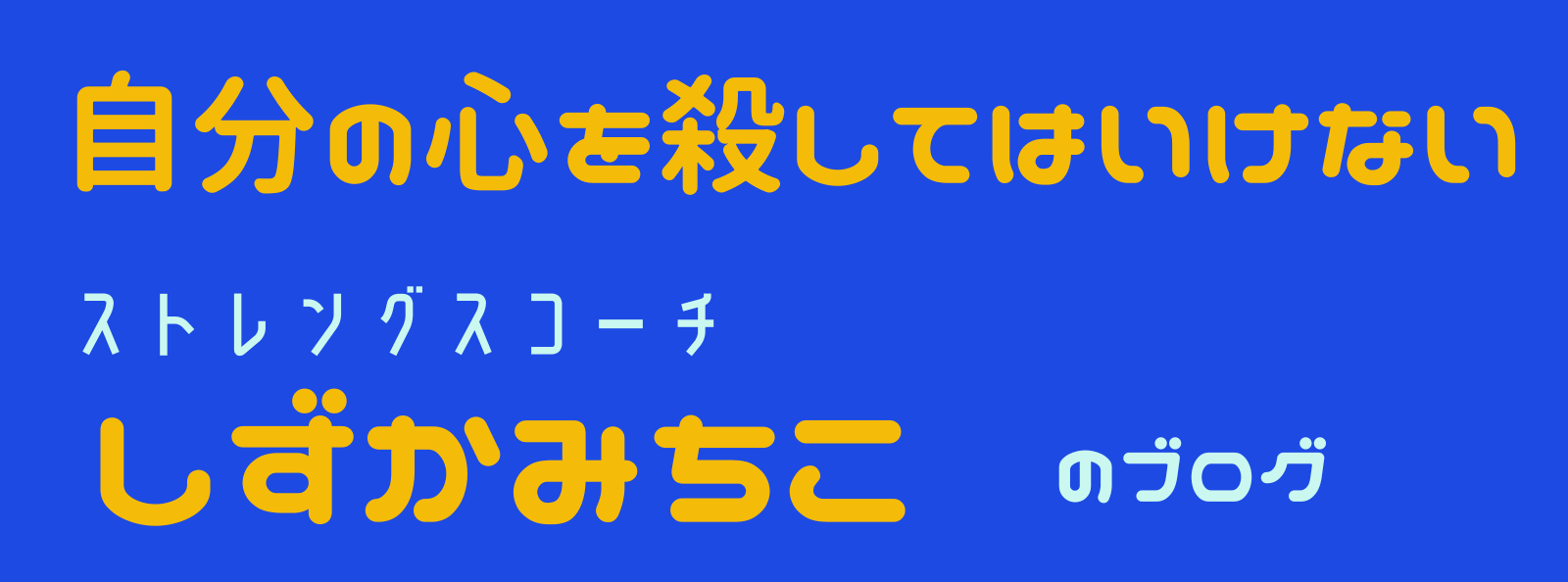自分を知る人が一人もいない街で人生をやり直そうとした話
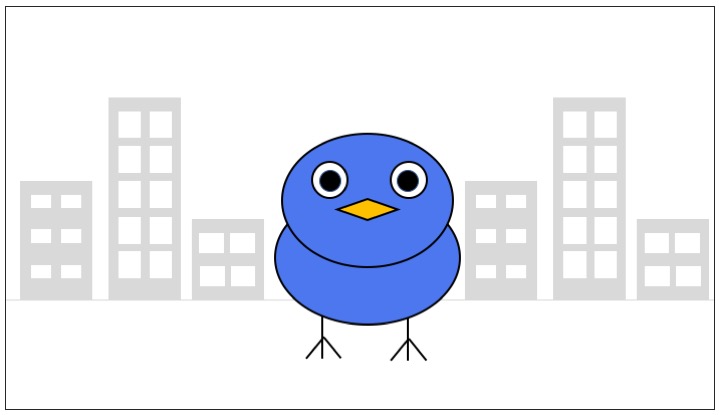
人生をやり直すための彷徨い
仙台にて
ずっと自分が嫌いだった。
周囲の顔色を伺い、周囲の後押しがないと動けない自分が嫌だった。
友人たちは私を常に勇気付けてくれていた。だから毎日は楽しかったけれど、友人が側にいない時間は辛かった。
仙台は、東北の中では都会だけれど、街自体は狭い。
誰にも何も言わなくても、「昨日、一番町にいたでしょ。買い物?何買ったの?一緒にいたのは誰?」などと聞かれてしまう。
いつも見張られているような気がしていた。
縛られている感覚があって、息苦しかった。
この場所から逃げ出したかった。
私のことを知っている人が一人もいないところにいって、人の目を気にせず自分の好きなように生きてみたかった。
違う自分に生まれ変わりたかった。
だから、知り合いのいない青森の大学に進学を決めた。
青森にて
大学に進んでも、状況は変わらなかった。
両親の目はなくなったが、誰かに見張られている感覚は無くならなかった。
自由気ままな一人暮らしだったのに、縛られている感覚があって、息苦しかった。
こんな生活が嫌で仙台を飛び出したのに、同じ状況になっていた。
もう一度、私のことを知っている人が一人もいないところにいって、今度こそ生まれ変わろうと思った。
福岡にて
福岡の会社に就職した。
福岡といっても博多でも天神でもなく、市町村でいうところの町、見渡す限り畑が広がる町だった。
同期の女の子たちとはすぐに仲良くなれた。
小さい会社なので、全社員と顔見知りになって、飲みに行ったりするようになった。
しかし狭い社会に息苦しさを感じるようになった。
ほとんど話したこともないような人に、「昨日の夜、車なかったね。どこ行っていたの?」などと聞かれる生活が辛かった。
欠員が出た大阪に転勤を願い出た。
でも、気づいてもいた。
青森に行っても、福岡に行っても、状況は変わらなかった。
いくら場所を変えても、生まれ変わることはできないのだ。
私は、誰かに見張られながら生きていくしかないんだ。
絶望と諦めを荷台に乗せて、大阪へ向かって車を走らせた。
人生を変えた出会い
大阪にて
大阪は、カラフルな街だった。
実際、カラフルな洋服を着ている人が多かった。
目立つのが嫌で灰色と紺とベージュと茶色の服しか着ていなかった私は、目の前に広がる華やかな世界に驚いた。
大阪といえば目に浮かぶ、虎の顔が描いてあるTシャツを着たおばちゃんを実際に見て驚いたけれど、若い人も独特だった。
当時、天使の羽を背中につけるのが流行っていたらしく、アメ村のあたりには天使がたくさんいた。
それどころか、水引で作られた鶴を背負っている人までいた。
鶴を見た時の衝撃は、今でも忘れられない。
雷に打たれたような衝撃だった。
頭の中に「これでいいんだ!」という声が響き渡った。
自分が好きな服を、好きなように着ていいんだ!
洋服どころか、水引だって着ちゃっていいんだ!
一着のスカート
ある日、私は、ショーウィンドウのマネキンが着ていたスカートに一目惚れした。
明るい水色をベースに、白い花びらとオレンジのめしべを持つ花が無数に描かれたスカートだった。
てろんとした薄い生地で、裾の方だけフレアになっている、女の子らしいかわいい服だった。
今までだったら、私には縁がないと、目を伏せて立ち去っていただろう。
しかし、ここは大阪。鶴を背負っても許される街。
私だって、好きな服を着てもいいかもしれない。
思い切って店の中に入った。
でも、明るい水色のスカートを手に取る勇気はなかった。
代わりに、色違いの紺色ベースのスカートを手に取った。
紺色なら、私が着ても許してもらえるだろうか。
それでもチェック以外の柄物の服なんて着たことないし、柔らかい素材の服も着たことがない。
私にとっては大冒険だった。
敗北と、そして
試着室から出てきた私は無様だった。
柔らかい生地が貧弱な下半身に沿ってラインを描き、紺色がさらにシルエットを引き締め、不恰好だった。
悲しかった。恥ずかしかった。みじめだった。
やっぱり私には、こういう女の子らしいスカートは似合わないんだ。
それなのにかわいいスカートに挑戦した私を、店員さんは哀れに思っているだろう。
店員さんでさえ、「お似合いですね」「かわいいですよ」といったお決まりのセリフを言わなかった。その代わり、こう言った。
「サイズはいいみたいですね。少々お待ち下さい。」
すぐに店員さんは戻って来た。
「これなんかいいと思いますよ。」
私が手渡されたのは、あの一目惚れした水色のスカートだった。
こんな無様な姿を見せたのだから、もう怖いものはない。
泣きそうな気持ちを奮い立たせながら、水色のスカートを身につけた。
鏡には、さっきとは別の人間が写っていた。
ラインはさっきと変わらないはずなのに、水色とオレンジがシルエットを柔らかく見せていた。
よく男性に間違えられる骨だらけの体型が、生地と色のやわらかさが加わって、女性らしくなっていた。
無言で目を見張る私に、店員さんは声をかけた。「お似合いですね。」
このスカートとの出会いが、私の人生を変えたのである。
私を縛り付けていたもの
犯人は、私
私には、綿の服しか似合わないはずだった。
地味な色しか着てはいけないと思っていた。
でも、それは単なる思い込みだった。
それをこのスカートが気づかせてくれた。
ずっと私を苦しめていた、いつも見張られているような縛られているような感覚の正体が分かった。
私を見張り、縛り付けているのは、私自身だったのだ。
どんなに私を知る人がいない場所に行っても、生まれ変われないのは当たり前だった。
私が私を縛り付けている限り、生まれ変われるわけがないのだ。
生まれ変わるために必要なのは、周辺の環境を変えることではなく、自分自身を縛ることを止めることだったのだ。
それに気づかず、仙台から青森、福岡、大阪と、引越しを繰り返すなんて、いったい何をやっていたのだろう。
生まれ変わるために必要なもの
あのスカートに出会ってから15年。
自分を縛る思い込みから、少しずつ自分を解放してきた。
好き、やってみたい、と思ったことは、周囲が反対しても常識はずれなことでも挑戦するようにしている。
今でもまだ、自分に潜む思い込みに気づいて驚く毎日だ。
でも、いつの間にか息苦しさはなくなった。
私を見張る目に気がついたら、縛らないでよ、と声を掛けることもできる。
もうどこにも逃げ出す必要はなくなった。
あの日車に積んだ絶望と諦めも、どこかの街に置いてきた。
生まれ変わるのに必要なのは、周辺の環境を変えることではなく、自分自身が変わること、ただそれだけだったのだ。
関連記事
https://koto1.com/archives/2963
https://koto1.com/archives/8576