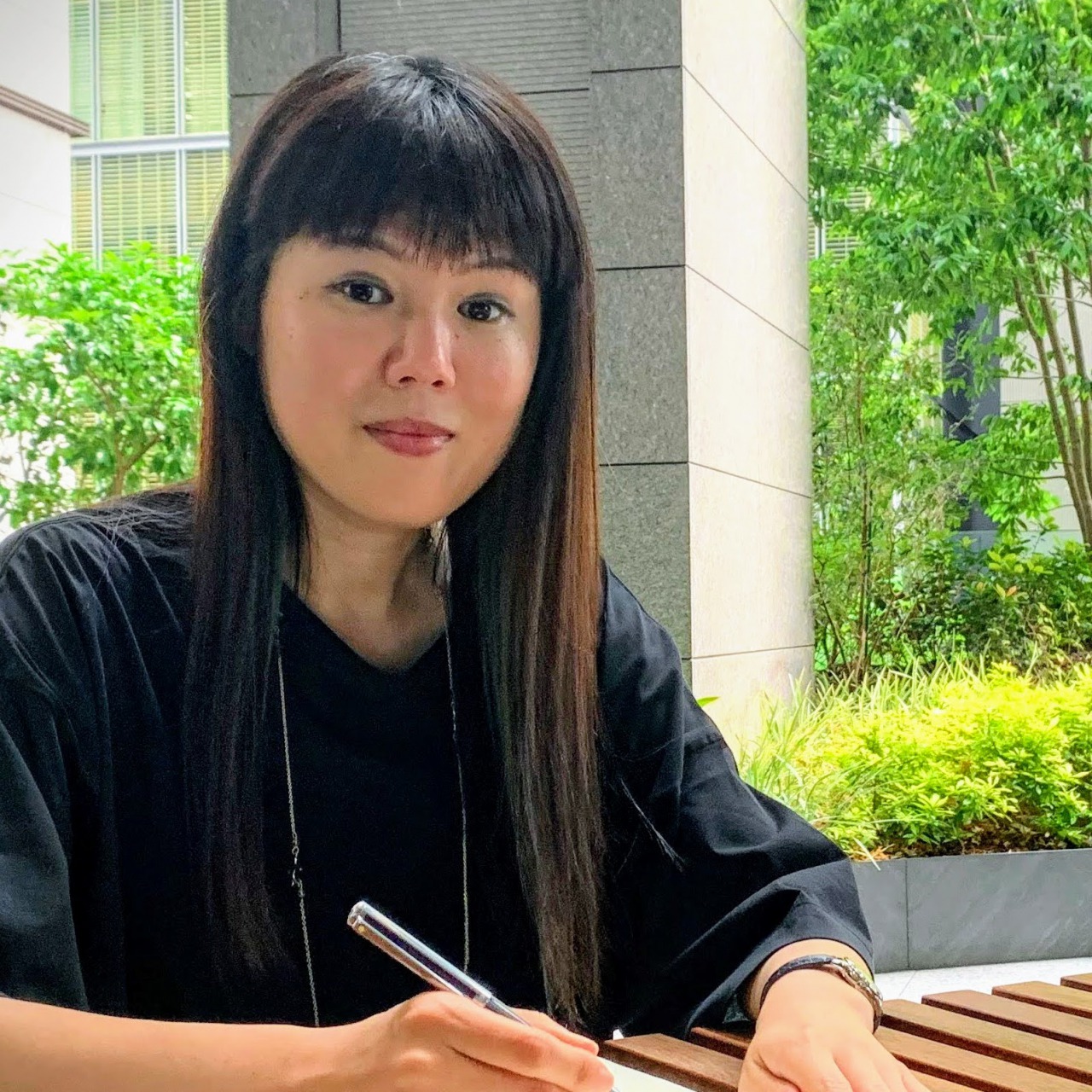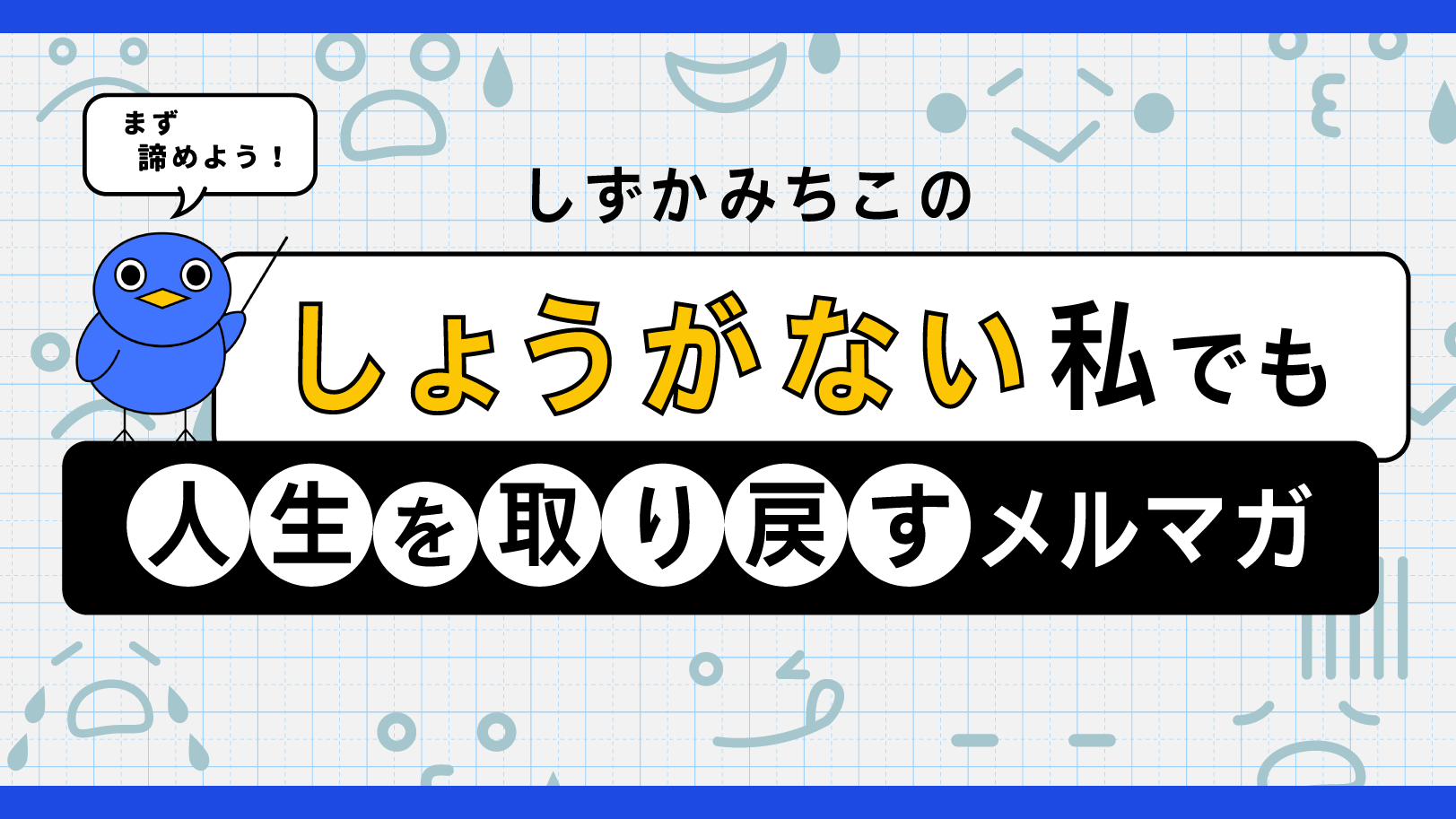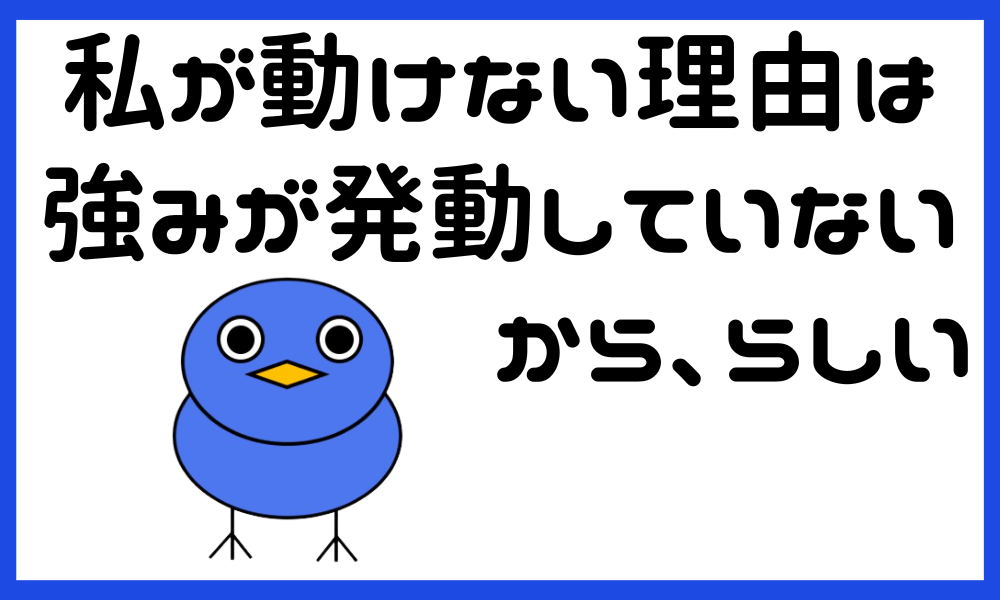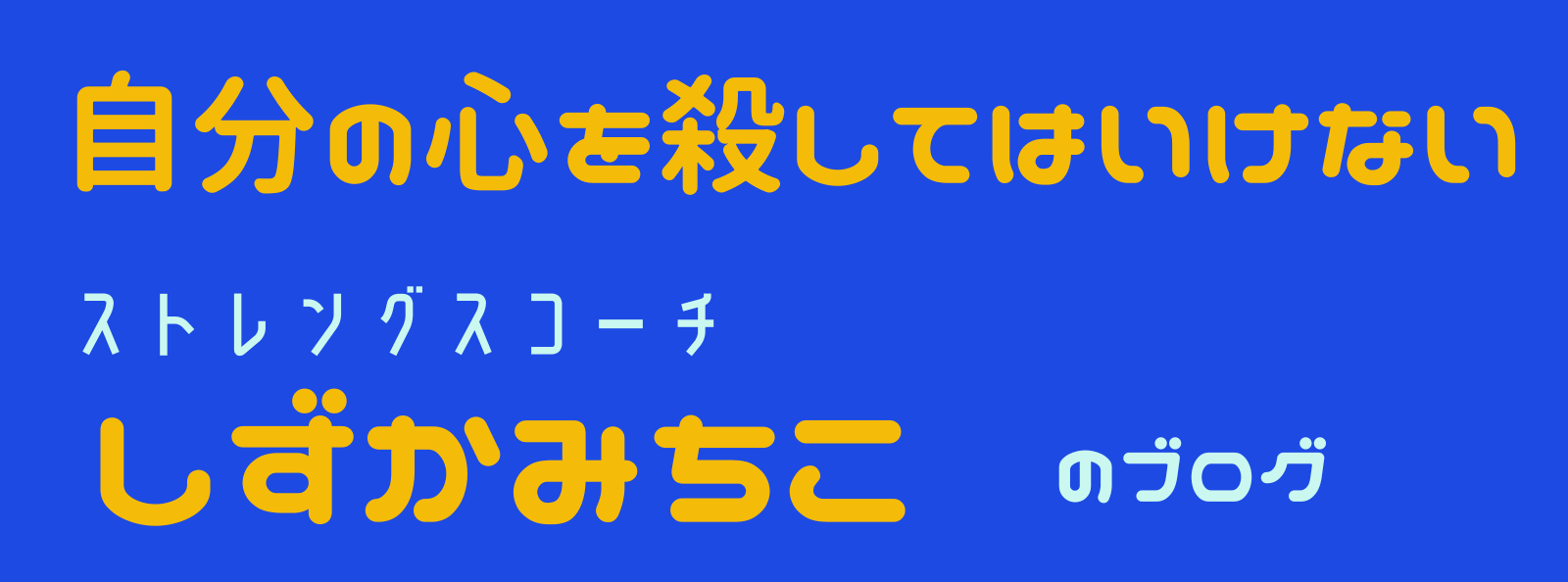居心地の悪さを我慢して、羊の皮をかぶっているライオンたちへ

僕は羊だ
僕は羊の群れの一員だ。
視界には、見渡す限りの羊たち。
モコモコの身体を寄せ合って、温めあう。
とても居心地のいい場所だ。
僕たちは足元の草を分け合って食む。
誰かが草を食み始めたら、僕たちもそこに行って一緒に草を食む。
僕たちはいつも足元を見て、草が生えているところを探している。
一人占めするヤツなんていない。
とても居心地のいい場所だ。
日が暮れ始めたら、誰ともなく言い出して、小屋に戻る。
皆がぞろぞろ小屋に向かって歩き出すから、僕も一緒に歩くんだ。
え?牧羊犬が僕らを追い立てているって?
それはよく分からない。
群れの真ん中にいる僕には犬は見えないよ。
ただ皆が小屋に向かって歩き出すから、僕も一緒に歩くんだ。
だって一人で外に取り残されたら、寂しいもんね。
ここは皆がいつも一緒に行動するんだよ。
とても居心地のいい場所だ。
そう。とても居心地のいい場所だ。
皆が温めあうんだよ。居心地がいいに決まってる。
皆で食料を分け合うんだよ。居心地がいいに決まってる。
いつも皆で一緒に行動するんだ。居心地がいいに決まってる。
居心地がいいに決まってる。
居心地がいいに決まってる。
居心地がいいに決まってる。
ここのことを居心地が悪いなんて思ってはいけない。
ここは居心地がいい場所のはずなんだ!
でも僕は
でも僕は、ときどきこう思うんだ。
身を切るようなからっ風に身体をさらして、大声で叫んでみたい。
足元に生えている草を探すのではなく、自分の力で食べ物を獲得してみたい。
皆で一緒に行動するのではなく、自分の行きたいところに行ってみたい。
仲間に話してみたことがある。
ある羊はこう言った。「羊が大声で叫びたいなんて大それた夢を見るなよ」
別の羊はこう言った。「草なんてあちこちに生えてるぜ?自分で獲得する意味ないじゃん」
違う羊はこう言った。「俺たちは一人じゃ何もできないんだから止めとけよ」
そう。せっかくこんなに居心地のいい場所にいるのに、こんなことを思う僕が悪いんだ。
夢想家で、意味のないことをしたがる、一人じゃ何もできないどうしようもない羊なんだ。
でも、でも…。
僕は、自分の足で思いっきり走ってみたい。
でも、でも…。
そんなことしたら嫌われて、群れにいられなくなる。
でも、でも、でも!
夢を見た
ある日、僕は夢を見た。
立派なタテガミをなびかせた金色の動物が、夕日に向かって佇んでいた。
その動物はライオンというらしい。
夢の中でライオンは、僕をじっと見て、ひとこと吼えた。
ガオーーーーッ!!!
僕の回りにいた羊たちは逃げるために走りだした。
僕も走った。
小屋に向かって走り出した僕の目に、夕日にキラキラ輝くライオンのタテガミが映った。
水桶に映るもの
目が覚めても、金色に輝くライオンのタテガミが忘れられなかった。
気持ちを落ち着けるために水を飲もうと、僕は水桶に向かった。
水桶を覗き込んだとき、僕は驚いた。
そこにはライオンが映っていたのだ。
これは…僕?
僕が首を右に傾げると、水桶の中のライオンも同じ方向に首を傾げる。
僕が口を開けると、水桶の中のライオンも口を開ける。
僕は仲間に聞いてみた。
「ねえ、僕って羊だよね?ライオンじゃないよね?」
仲間たちは僕の方を碌に見ずに口々に答えた。
「お前が羊じゃなきゃ何だって言うんだよ」
「ライオン?何それ?寝ぼけてんじゃねえよ」
「お前は羊に決まってるだろ。お前は俺たちと同じ羊なんだよ」
「何?お前、羊以外の何かになりたいの?バッカじゃねえの」
「お前さー、そんなこと考えるなんてよっぽど暇なんだな。そんな暇あるなら草でも探そうぜ」
仲間たちはケラケラと笑いながら歩き出した。
僕はモヤモヤとした気持ちを抱えながら、仲間たちと共に歩き出した。
その日もいつもと同じ一日だった。
モコモコの身体を寄せ合って、温めあう。
誰かが草を食み始めたら、僕たちもそこに行って一緒に草を食む。
そろそろ日暮れだ。
誰ともなく小屋に戻ろうと言い出すだろう。
ライオン、再び
群れがざわついたのは、その時だった。
柵の向こうに、一頭の金色の動物がいた。
夕日に照らされたタテガミがキラキラ輝くライオンだった。
夢で見た光景と同じだ!
驚きのあまり立ちすくんだ僕を、ライオンは真っ直ぐ見つめた。
そして吼えた。
ガオーーーーッ!!!
僕の回りにいた仲間たちは逃げるために走りだした。
僕も逃げなくちゃ。
でも、僕の足は動かなかった。
僕の身体の内部から熱いものが込み上げてきた。
その熱が僕の全身に広がり、僕の口から飛び出した。
ガオーーーーッ!!!
仲間たちは、僕を化け物を見るような目で見ると、慌てふためいて逃げていった。
皆、小屋に逃げていき、僕は一人になった。
柵の向こうのライオンは、まだ僕を見ていた。
そして、ゆっくりと方向を変えて歩き出した。
待って!僕は…。僕は…!
僕は意を決して、柵に向かった。
一歩目はゆっくりと、そこからどんどんスピードを上げていき、全速力で走り、そして、僕は飛んだ。
僕が柵を超えるところを、ライオンは見ていた。
ライオンは一回軽く頷くと、歩き出した。
僕もその後を歩き出した。
今、僕は
僕は今、ライオンの群れで暮らしている。
羊の仲間たちのように常にべったり一緒にいるわけではないけれど、仲間の存在を感じることができている。
僕は自分で餌を探せる。
好きな時に好きなところで眠りにつく。
かつての僕は、羊以外の動物がこの世にいるなんて考えたことがなかった。
羊たちから嫌われたら、この世でひとりぼっちになると思っていた。
でも実際は違った。
身体の中から湧き上がる熱に身を任せてみたら、新たな仲間と出会うことができた。
もしかしたら羊の群れの方が楽に生きていけたかもしれない。
でも、今僕がいるここが、本当の僕の居場所だ。
僕が一番僕らしくいられる場所なんだ。
寒い日があっても、餌にありつけない日があっても、僕が僕として生きられる今を、僕は愛している。
今の僕には夢がある。
僕がライオンとなって吼えた時、逃げ惑う羊の中に金色の脚が見えたんだ。
まだあそこには羊の皮をかぶったライオンがいるはずだ。
まだ自分自身がライオンと気づかないまま、一生懸命羊になろうとしているライオンがいるはずなんだ。
羊の群れの中で居心地が悪い思いをしている、羊の皮をかぶったライオンたちへ。
あの日、一頭のライオンが僕を迎えに来てくれたように、今度は僕が君を迎えに行く。
その日まで、君の中にある熱を、どうか失わないでいて。